 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
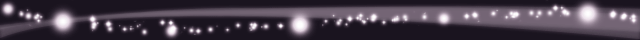
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
石榴(ざくろ)の月~愛され求められ奪われて~
第8章 第二話・参
「何で、お前さんが謝るのよ? 謝るのは私の方じゃない。こんなになって、それでもまだお前さんの許にのこのこ帰ってくるなんて、よくそんな汚れた身体で帰ってくるなって、何で私を責めないの?」
「止せ」
嘉門の言うとおりだった。お民の身体はやはり、嘉門と過ごした幾つもの夜を忘れてはいなかった。久しぶりに昨夜、嘉門に抱かれたお民は、烈しい愛撫に幾度も身をくねらせ、歓喜の声を上げたのだ。
それが、源治への裏切りでなくて、何と言えよう。
「私はもう駄目。身体だけじゃなくて、心まで汚れちまった。お前さんだって、こんな女、良い加減に愛想が尽きるでしょう」
自嘲するかのようなお民の言葉は、源治の怒声によってかき消された。
「止さないか!」
「だって、お前さん。私、お前さんに合わせる顔がなくて。でも、諦めが悪いから、また帰ってきちゃった。どうしても、お前さんの顔がもう一度見たかったから、せめて出ていくなら、大好きな男の顔を見てから、行きたかったから」
「出て行かせるものか。お前は俺の女房だぞ? 俺以外の男の、どこに行くっていうんだよ」
「こんな私でも、お前さんはまだ女房だと思ってくれるの?」
お民の眼から大粒の涙が溢れ落ちた。
「当たり前じゃねえか。お前は俺にとって、一生にただ一人の女だからな」
「―嬉しい」
お民は源治の胸に縋りつく。
「前にも言ったろう? たとえ、何があっても、お前はお前だ。俺は、そのままの今のお前が好きなんだ」
そういえば、去年の秋、嘉門の屋敷から暇を取って帰されてきたときも、源治は同じことを言った。
―俺は、そのままの、今のお前が好きなんだ。何があったとしても、お前はお前で、変わることはねえよ。
「だから、もう何も余計なことは考えるな。お前の居場所は、俺の側だ。出ていくなんてことも、二度と言わねえでくれ」
源治の手がお民の髪を撫でる。お民の頭を両手で抱え込み、源治は唇をその豊かな黒髪に押し当てた。昨夜の嘉門も閨でお民の髪に口づけたけれど、嘉門の仕草と同じはずなのに、込められた意味合いが全く違う。
「止せ」
嘉門の言うとおりだった。お民の身体はやはり、嘉門と過ごした幾つもの夜を忘れてはいなかった。久しぶりに昨夜、嘉門に抱かれたお民は、烈しい愛撫に幾度も身をくねらせ、歓喜の声を上げたのだ。
それが、源治への裏切りでなくて、何と言えよう。
「私はもう駄目。身体だけじゃなくて、心まで汚れちまった。お前さんだって、こんな女、良い加減に愛想が尽きるでしょう」
自嘲するかのようなお民の言葉は、源治の怒声によってかき消された。
「止さないか!」
「だって、お前さん。私、お前さんに合わせる顔がなくて。でも、諦めが悪いから、また帰ってきちゃった。どうしても、お前さんの顔がもう一度見たかったから、せめて出ていくなら、大好きな男の顔を見てから、行きたかったから」
「出て行かせるものか。お前は俺の女房だぞ? 俺以外の男の、どこに行くっていうんだよ」
「こんな私でも、お前さんはまだ女房だと思ってくれるの?」
お民の眼から大粒の涙が溢れ落ちた。
「当たり前じゃねえか。お前は俺にとって、一生にただ一人の女だからな」
「―嬉しい」
お民は源治の胸に縋りつく。
「前にも言ったろう? たとえ、何があっても、お前はお前だ。俺は、そのままの今のお前が好きなんだ」
そういえば、去年の秋、嘉門の屋敷から暇を取って帰されてきたときも、源治は同じことを言った。
―俺は、そのままの、今のお前が好きなんだ。何があったとしても、お前はお前で、変わることはねえよ。
「だから、もう何も余計なことは考えるな。お前の居場所は、俺の側だ。出ていくなんてことも、二度と言わねえでくれ」
源治の手がお民の髪を撫でる。お民の頭を両手で抱え込み、源治は唇をその豊かな黒髪に押し当てた。昨夜の嘉門も閨でお民の髪に口づけたけれど、嘉門の仕草と同じはずなのに、込められた意味合いが全く違う。
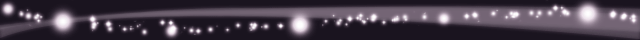
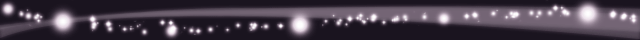
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


