 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
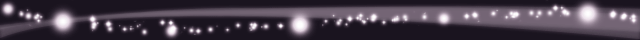
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
石榴(ざくろ)の月~愛され求められ奪われて~
第8章 第二話・参
すごぶる美人というわけではなく、ごく普通の美人ではあるが、光り輝く膚の雪のように白さがその並の美しさを極上と言って良いほどに変えている。例えていえば、かすかに紅色に染まった純白の百合の花、更にその花のひとひらに朝露を置いたような、そんな風情の女だ。
女の女将が見てさえ、思わず眼を奪われるほどの美貌、匂いやかな色香がある。あの男がこの女にあれほどまでに溺れているのも無理からぬことといえた。
「何も食べないで、一体、どういうつもりだえ。見せつけに飢え死にでもしようって算段かい」
二度目に覗いたときも、まだ女は裸のまま虚ろな眼をして座っていた。女の向かいに座り、女将はわざと蓮っ葉な口調で言った。
「とにかく、何か着たらどうなんだい」
言ってやると、女はゆっくりと首を振る。
女将は周囲を見回して、呆れ顔になった。
「なるほど、そういうことかえ」
何とも念の入ったことに、あの侍は女の身につけていた着物をすべて持ち去ったらしい。つまり、目下のところ、女が着物を着ようにも、着ていた着物がご丁寧に長襦袢や腰紐に至まですべてなくなっているのだ。
そういえば、帰り際、あの男が何度も言っていたっけ。
女にはあらかじめ用意していた緋色の長襦袢以外は一切身につけさせてはならない、と。
「全く、あの男はうちの店を女郎屋と勘違いしてるんじゃないだろうね」
女将は大仰に溜息を洩らした。
「まぁ、客を取る女郎じゃあるまいに、あんなもの着たくもないだろうけど、幾ら何でもそのままんじゃ風邪を引いちまうよ。厭でも、着ておくんだね」
女将は衣桁から長襦袢を取ると、女の剥き出しの肩にかけてやった。
女は別に抵抗もせず、ただうつむいているだけだ。まるで人形が着物を着せかけられているように微動だにしない。
女将はそんな女を見て、また吐息をついた。
「あたしは、あんたみたいな娘をたくさん見たよ。あたしは、たった二人きりの姉さんと同じ女郎屋に売られてね。初めて客を取った水揚げの夜、姉さんは自分で生命を絶った。あたしより四つ上の十六だったけ。あんた―、あのときの姉さんと同じ眼をしてる」
女将が話している中に、虚ろな女の眼にかすかに光が戻った。
女の女将が見てさえ、思わず眼を奪われるほどの美貌、匂いやかな色香がある。あの男がこの女にあれほどまでに溺れているのも無理からぬことといえた。
「何も食べないで、一体、どういうつもりだえ。見せつけに飢え死にでもしようって算段かい」
二度目に覗いたときも、まだ女は裸のまま虚ろな眼をして座っていた。女の向かいに座り、女将はわざと蓮っ葉な口調で言った。
「とにかく、何か着たらどうなんだい」
言ってやると、女はゆっくりと首を振る。
女将は周囲を見回して、呆れ顔になった。
「なるほど、そういうことかえ」
何とも念の入ったことに、あの侍は女の身につけていた着物をすべて持ち去ったらしい。つまり、目下のところ、女が着物を着ようにも、着ていた着物がご丁寧に長襦袢や腰紐に至まですべてなくなっているのだ。
そういえば、帰り際、あの男が何度も言っていたっけ。
女にはあらかじめ用意していた緋色の長襦袢以外は一切身につけさせてはならない、と。
「全く、あの男はうちの店を女郎屋と勘違いしてるんじゃないだろうね」
女将は大仰に溜息を洩らした。
「まぁ、客を取る女郎じゃあるまいに、あんなもの着たくもないだろうけど、幾ら何でもそのままんじゃ風邪を引いちまうよ。厭でも、着ておくんだね」
女将は衣桁から長襦袢を取ると、女の剥き出しの肩にかけてやった。
女は別に抵抗もせず、ただうつむいているだけだ。まるで人形が着物を着せかけられているように微動だにしない。
女将はそんな女を見て、また吐息をついた。
「あたしは、あんたみたいな娘をたくさん見たよ。あたしは、たった二人きりの姉さんと同じ女郎屋に売られてね。初めて客を取った水揚げの夜、姉さんは自分で生命を絶った。あたしより四つ上の十六だったけ。あんた―、あのときの姉さんと同じ眼をしてる」
女将が話している中に、虚ろな女の眼にかすかに光が戻った。
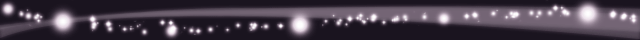
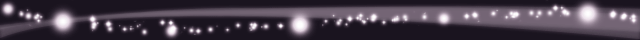
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


