 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
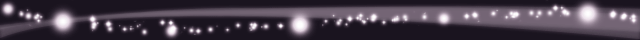
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
隷婦 狙われた淫らな発情妻・実雅子 ~中出しの快楽に堕ちて~
第16章 実雅子の過去
「キモいか。ま、わからなくもないか。誕生日を教えていないのに勝手に調べて、プレゼントを渡されてもな」
と、理解を示す反町。
「そうかな。好きな女の子を喜ばせるためなら、それくらいするだろ」
と、気色ばんで反論する斎田。身に覚えがあるのか、それとも、その話の男性に同情したのか、わからないが、その男は、〇〇学院大学の学生であるということは、間違いなく後輩であるのだから。
「ま、そうだな。俺も、大学の頃。○○女学院の高校生で、笑顔が可愛い子がいて、勇気を出して、ラブレターを書いて渡したら、内容も読まずに『やめてください』と、真顔で睨まれたよ」
頭を掻く重村。
「でも、合コンとかはありましたよね」
と、話したのは、関。
「あったかな。俺は経験がないよ」
と、苦笑いしたのは、志温と、佐藤。
「俺は〇〇女子大とか、○○○女子大だった」
と、話したのは重村。
「どうだろう。○○女学院の中学・高校は、当たり前だけどなかったけど、ま、アメフト部というだけで、○○女学院大学の学生からは野蛮人扱いだったよな」
と、話すのは斎田。
「○○女学院大学の学生は兎も角、○○女学院の中学・高校の生徒は、知性美があったけど、その視線に、俺たちに対する侮蔑が宿っていたように思うのは被害妄想かな」
と、苦笑したのは、関。
「関も俺も、〇〇学院大学の附属だから、経験があるけど、大学からなら、それほどないと思っていました」
と、志温が話した。
「関も清水も、附属か?だったら、実雅子と同じ32歳だし、中学・高校時代に出会っている可能性もあるんじゃないのか?」
と、聞いたのは反町。
「そうなりますね。でも、名前に聞き覚えはない」
と、答えた関。
「そもそも、名前を知る機会すらなかったよな」
と、話したのは志温。
「当然よ。〇〇学院大学の附属なんて、実雅子に言わせれば、『親の七光り、親の脛をかじるだけのボンボンのボンクラの集まり』だもの。相手にされないわ」
と、関と夫の志温を煽るサラン。
と、理解を示す反町。
「そうかな。好きな女の子を喜ばせるためなら、それくらいするだろ」
と、気色ばんで反論する斎田。身に覚えがあるのか、それとも、その話の男性に同情したのか、わからないが、その男は、〇〇学院大学の学生であるということは、間違いなく後輩であるのだから。
「ま、そうだな。俺も、大学の頃。○○女学院の高校生で、笑顔が可愛い子がいて、勇気を出して、ラブレターを書いて渡したら、内容も読まずに『やめてください』と、真顔で睨まれたよ」
頭を掻く重村。
「でも、合コンとかはありましたよね」
と、話したのは、関。
「あったかな。俺は経験がないよ」
と、苦笑いしたのは、志温と、佐藤。
「俺は〇〇女子大とか、○○○女子大だった」
と、話したのは重村。
「どうだろう。○○女学院の中学・高校は、当たり前だけどなかったけど、ま、アメフト部というだけで、○○女学院大学の学生からは野蛮人扱いだったよな」
と、話すのは斎田。
「○○女学院大学の学生は兎も角、○○女学院の中学・高校の生徒は、知性美があったけど、その視線に、俺たちに対する侮蔑が宿っていたように思うのは被害妄想かな」
と、苦笑したのは、関。
「関も俺も、〇〇学院大学の附属だから、経験があるけど、大学からなら、それほどないと思っていました」
と、志温が話した。
「関も清水も、附属か?だったら、実雅子と同じ32歳だし、中学・高校時代に出会っている可能性もあるんじゃないのか?」
と、聞いたのは反町。
「そうなりますね。でも、名前に聞き覚えはない」
と、答えた関。
「そもそも、名前を知る機会すらなかったよな」
と、話したのは志温。
「当然よ。〇〇学院大学の附属なんて、実雅子に言わせれば、『親の七光り、親の脛をかじるだけのボンボンのボンクラの集まり』だもの。相手にされないわ」
と、関と夫の志温を煽るサラン。
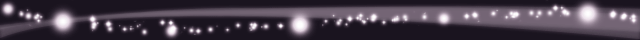
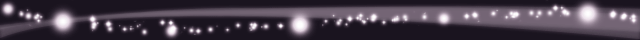
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


