 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
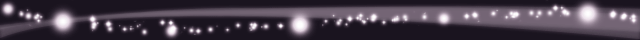
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
石榴(ざくろ)の月~愛され求められ奪われて~
第8章 第二話・参
―まぁ、よく言う。
―だって、お前の顔の方にこそ何か書いてあるぜ。
―えっ。
お民が愕いて頬に手を添えると、源治が大笑いした。
―俺のことが好きで好きでたまらねえ、お民は源さんに心底惚れてますって書いてあらあ。
―お前さん、また私をからかったんですね。もう、知りません!
お民がむくれると、源治が笑い転げながら言う。
―ちったァ、良いじゃねえか。所帯を持つ前は俺がさんざんお前にからかわれてたんだから。これくらいは可愛いもんだぜ。
―あれは、からかったんじゃありません。本気でお前さんのことを思って言ってたんですよ。親切、親切。
そこまで言って、二人は顔を見合わせて、ひとしきり笑った。
笑いながら、お民は涙を流していた。
―何だよ、どうして、泣くんだ?
―あんまりおかしかったから、涙が出ちまったんですよ。
我ながら、あまり上手くない言い訳だと思ったけれど、他に思いつかなかった。
源治は訝しげにお民を見つめていた―。
あのときの源治の笑顔を思い出しただけで、胸が締めつけられるように切ない。
何も知らぬ良人を、お民は騙しているのだ。
腹の子を堕ろすつもりはなかった。嘉門との間に最初に身籠もった子を、お民は酷い方法で抹殺してしまった。結果的にお民は何をしたわけではないけれど、一度は腹の子もろとも死のうと自害しようとしたことさえある。
実の母親に疎まれながら、この世の光を見ることもなく逝った子が哀れでならなかった。もう、あのときと同じ過ちは繰り返したくはない。
しかし、源治もまた、お民にとっては大切な―恐らく、自分自身よりも大切な存在だ。その源治を裏切ることはできない。
―そなたはもう、この俺から逃れられぬ。
ふいに嘉門の惛い声が耳奥で響く。
三月前、出合茶屋で手込めにされた夜、嘉門の囁いた科白をふと思い出した。
―そなたの身体は既に俺に馴染んでいる。今になって亭主の許に帰ったとしても、昔のように恋しい男と暮らせるとは思うな。
―だって、お前の顔の方にこそ何か書いてあるぜ。
―えっ。
お民が愕いて頬に手を添えると、源治が大笑いした。
―俺のことが好きで好きでたまらねえ、お民は源さんに心底惚れてますって書いてあらあ。
―お前さん、また私をからかったんですね。もう、知りません!
お民がむくれると、源治が笑い転げながら言う。
―ちったァ、良いじゃねえか。所帯を持つ前は俺がさんざんお前にからかわれてたんだから。これくらいは可愛いもんだぜ。
―あれは、からかったんじゃありません。本気でお前さんのことを思って言ってたんですよ。親切、親切。
そこまで言って、二人は顔を見合わせて、ひとしきり笑った。
笑いながら、お民は涙を流していた。
―何だよ、どうして、泣くんだ?
―あんまりおかしかったから、涙が出ちまったんですよ。
我ながら、あまり上手くない言い訳だと思ったけれど、他に思いつかなかった。
源治は訝しげにお民を見つめていた―。
あのときの源治の笑顔を思い出しただけで、胸が締めつけられるように切ない。
何も知らぬ良人を、お民は騙しているのだ。
腹の子を堕ろすつもりはなかった。嘉門との間に最初に身籠もった子を、お民は酷い方法で抹殺してしまった。結果的にお民は何をしたわけではないけれど、一度は腹の子もろとも死のうと自害しようとしたことさえある。
実の母親に疎まれながら、この世の光を見ることもなく逝った子が哀れでならなかった。もう、あのときと同じ過ちは繰り返したくはない。
しかし、源治もまた、お民にとっては大切な―恐らく、自分自身よりも大切な存在だ。その源治を裏切ることはできない。
―そなたはもう、この俺から逃れられぬ。
ふいに嘉門の惛い声が耳奥で響く。
三月前、出合茶屋で手込めにされた夜、嘉門の囁いた科白をふと思い出した。
―そなたの身体は既に俺に馴染んでいる。今になって亭主の許に帰ったとしても、昔のように恋しい男と暮らせるとは思うな。
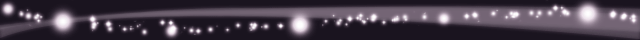
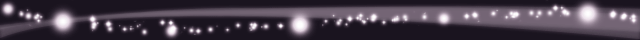
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


