 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
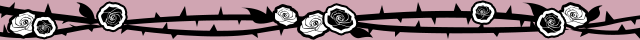
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
年の離れた妹
第2章 アパート
「母さんに連絡した?」
「ううん、今日は友達のところって言ってある」
「友達?」
妹は返事をせず下を向いた。僕はそれ以上言わず、恵津子の背中をポンポンと叩いた。横を歩く恵津子の目に、大粒の涙が溢れていた。
「えっちゃん、どうぞ…」
おどけた口調で背中を向け、僕は少し前屈みになった。妹は涙を溜めたまま僕を見ると、その目を腕でこすり涙を拭った。妹はすぐその意味を理解すると小さくニヤリと笑い、バッグをたすきに掛けた。そして子供のころ僕に飛びついておんぶをせがんだように、少し後ろに下がった。僕は背中に妹の衝撃を受ける覚悟をきめ、さらに前屈みになった。その瞬間、勢いをつけた妹が、僕の背中に飛び乗ってきた。小さな頃の妹と違い、160センチほどの恵津子の衝撃は予想以上だったが、僕はなんとか受け止めた。何人かの通行人が、驚いて僕たちを見ていた。
妹をおんぶしながら、僕はアパートまでの道を歩いていた。背中の妹は全てを僕に預けていた。僕の頬の横に恵津子の顔が覗いていた。その熱い吐息が、僕の口元に掛かっていた。恵津子の甘い匂いと一緒に、涙が僕の頬まで濡らしていた。無言のまま、妹は背中から僕を抱き締めていた。その時、僕の腕は恵津子の太ももを支えていた。そして僕の手は、妹の弾力あるお尻の下にあった。しかし妹はそのまま、僕の頬に顔を密着させていた。
「さあ、着いた」
僕は極力、明るく妹に声をかけた。妹はもう、泣き止んでいた。10分ほどの道すがら、恵津子はずっと僕に身体を預けていた。僕の腕は妹の汗で湿っていた。
「ありがとう、兄ちゃん」
妹はやっと、僕の背中から降りた。そしてワンピースの裾を直すと手で涙をぬぐい、照れ隠しに笑顔になった。僕は妹の肩をポンと叩くと、エレベーターに向かった。恵津子は僕の後を追いかけて、手を握ってきた。
「ううん、今日は友達のところって言ってある」
「友達?」
妹は返事をせず下を向いた。僕はそれ以上言わず、恵津子の背中をポンポンと叩いた。横を歩く恵津子の目に、大粒の涙が溢れていた。
「えっちゃん、どうぞ…」
おどけた口調で背中を向け、僕は少し前屈みになった。妹は涙を溜めたまま僕を見ると、その目を腕でこすり涙を拭った。妹はすぐその意味を理解すると小さくニヤリと笑い、バッグをたすきに掛けた。そして子供のころ僕に飛びついておんぶをせがんだように、少し後ろに下がった。僕は背中に妹の衝撃を受ける覚悟をきめ、さらに前屈みになった。その瞬間、勢いをつけた妹が、僕の背中に飛び乗ってきた。小さな頃の妹と違い、160センチほどの恵津子の衝撃は予想以上だったが、僕はなんとか受け止めた。何人かの通行人が、驚いて僕たちを見ていた。
妹をおんぶしながら、僕はアパートまでの道を歩いていた。背中の妹は全てを僕に預けていた。僕の頬の横に恵津子の顔が覗いていた。その熱い吐息が、僕の口元に掛かっていた。恵津子の甘い匂いと一緒に、涙が僕の頬まで濡らしていた。無言のまま、妹は背中から僕を抱き締めていた。その時、僕の腕は恵津子の太ももを支えていた。そして僕の手は、妹の弾力あるお尻の下にあった。しかし妹はそのまま、僕の頬に顔を密着させていた。
「さあ、着いた」
僕は極力、明るく妹に声をかけた。妹はもう、泣き止んでいた。10分ほどの道すがら、恵津子はずっと僕に身体を預けていた。僕の腕は妹の汗で湿っていた。
「ありがとう、兄ちゃん」
妹はやっと、僕の背中から降りた。そしてワンピースの裾を直すと手で涙をぬぐい、照れ隠しに笑顔になった。僕は妹の肩をポンと叩くと、エレベーターに向かった。恵津子は僕の後を追いかけて、手を握ってきた。
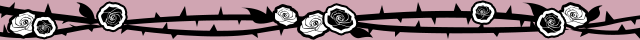
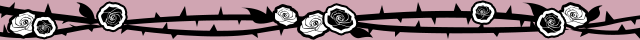
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


