 この作品は18歳未満閲覧禁止です
この作品は18歳未満閲覧禁止です
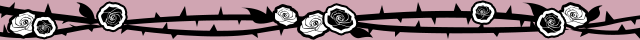
- 小
- 中
- 大
- テキストサイズ
欲求不満人妻・淫らに犯されて快楽堕ち。オリザ32歳の痴戯痴態
第6章 余韻から現実へ
「大丈夫ですか?」
齋藤がオリザに声を掛けた。オリザは、口に含んでいたものも飲み干して、
「うん。ちょっとむせただけ」
と、笑った。その笑顔を見て、齋藤は嬉しかった。あれだけ苦しそうにしていても笑ってくれることに。咲良は、フェラチオはしても、口に出すことを嫌がって、前戯と後戯でするくらい。終わったら洗面ですすぐ感じで、少なくともザーメンを飲むということはなかった。
「本当に?飲んでも大丈夫?」
齋藤にとっては、初めての性飲だけに、やはり心配は尽きない。重ねて聞くと、
「大丈夫よ。ちょっと鼻から出そうになったけどね」
想像するだけでも苦しそうだし、鼻から出そうになったということは逆流したのかもしれない。嘔吐する時も鼻から出そうになると痛いことは齋藤にもわかる。運動部の伝統で、どの部活も大学では吐くまで飲むが常態化していたからだ。
「無理しないでいいですよ」
齋藤がオリザの顔を見て話す。堅いフローリングのうえで並んで横になる二人。
「わたしばっかりイッちゃって。なんとか、最後は齋藤くんにもイってもらえてよかったわ」
オリザが齋藤を見て微笑んだ。実際、オリザは、満足していた。このまま、自分だけがイって、齋藤がイケなかったら、どうしようという思いもあったから。どちらからということもなく、手をつないで仰向けになった。
夫とはこんな経験はなかった。忙しい夫とはすれ違いばかり、そのうえ、浮気。そして、浮気相手に子供ができて、夫の横に立つのは、私ではないと思うようになっていたオリザにとって、今のこの位置は居心地は悪くなかった。
ただ、齋藤には彼女気取りかどうかは別として、そういう関係の女性がいる。その意味では、罪悪感があった。自分にとっての浮気相手と同じ位置に自分がいることを自覚していたから。齋藤は、どう思っているのか?気にはなっていたが、声に出すことはなかった。
一方、齋藤は、そもそもが咲良を恋人だと思ったことは一度もなかった。ただの彼女気取り。咲良が最初にエッチを求めたときも、乗り気ではなかった。ただ、冷たくできなかった。まして、突き放すこともできずに、ずるずると今の関係に至ってしまった。傍からは付き合っていると思われているのも知っている。最初は否定していたが、最近は、それも邪魔くさくなっていた。頭に過るのは、『既成事実』という言葉くらい。
齋藤がオリザに声を掛けた。オリザは、口に含んでいたものも飲み干して、
「うん。ちょっとむせただけ」
と、笑った。その笑顔を見て、齋藤は嬉しかった。あれだけ苦しそうにしていても笑ってくれることに。咲良は、フェラチオはしても、口に出すことを嫌がって、前戯と後戯でするくらい。終わったら洗面ですすぐ感じで、少なくともザーメンを飲むということはなかった。
「本当に?飲んでも大丈夫?」
齋藤にとっては、初めての性飲だけに、やはり心配は尽きない。重ねて聞くと、
「大丈夫よ。ちょっと鼻から出そうになったけどね」
想像するだけでも苦しそうだし、鼻から出そうになったということは逆流したのかもしれない。嘔吐する時も鼻から出そうになると痛いことは齋藤にもわかる。運動部の伝統で、どの部活も大学では吐くまで飲むが常態化していたからだ。
「無理しないでいいですよ」
齋藤がオリザの顔を見て話す。堅いフローリングのうえで並んで横になる二人。
「わたしばっかりイッちゃって。なんとか、最後は齋藤くんにもイってもらえてよかったわ」
オリザが齋藤を見て微笑んだ。実際、オリザは、満足していた。このまま、自分だけがイって、齋藤がイケなかったら、どうしようという思いもあったから。どちらからということもなく、手をつないで仰向けになった。
夫とはこんな経験はなかった。忙しい夫とはすれ違いばかり、そのうえ、浮気。そして、浮気相手に子供ができて、夫の横に立つのは、私ではないと思うようになっていたオリザにとって、今のこの位置は居心地は悪くなかった。
ただ、齋藤には彼女気取りかどうかは別として、そういう関係の女性がいる。その意味では、罪悪感があった。自分にとっての浮気相手と同じ位置に自分がいることを自覚していたから。齋藤は、どう思っているのか?気にはなっていたが、声に出すことはなかった。
一方、齋藤は、そもそもが咲良を恋人だと思ったことは一度もなかった。ただの彼女気取り。咲良が最初にエッチを求めたときも、乗り気ではなかった。ただ、冷たくできなかった。まして、突き放すこともできずに、ずるずると今の関係に至ってしまった。傍からは付き合っていると思われているのも知っている。最初は否定していたが、最近は、それも邪魔くさくなっていた。頭に過るのは、『既成事実』という言葉くらい。
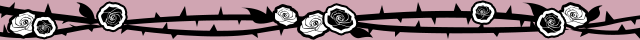
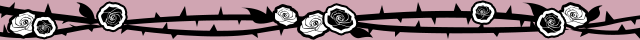
 作品検索
作品検索 しおりをはさむ
しおりをはさむ 姉妹サイトリンク 開く
姉妹サイトリンク 開く


